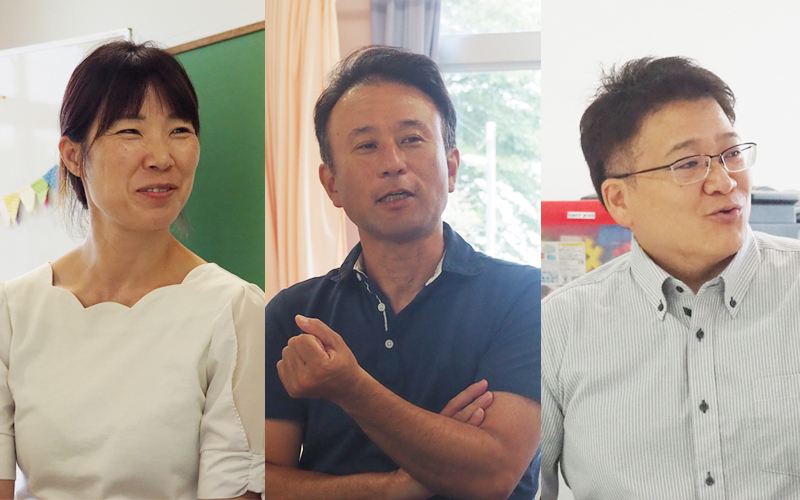生産者インタビュー
2025.11.13
農業の魅力を発信!
日本における農業は、高齢化による担い手不足、耕作放棄地の増加、気候変動など、課題は多岐にわたり深刻化を増しています。
そのような中、自然豊かな山口県岩国の地で、20代前半の頃からご夫婦で新規就農して23年。今では、約20種類もの新鮮な野菜を消費者に届け続ける隅さんご夫婦に、これまでの歩み、農業の醍醐味と苦労、そして将来への想いをお伺いしました。

のぞみファーム 隅 望さん・美穂さんご夫婦
農業を始めたきっかけ
望さん
今は葉物野菜を中心に栽培していますが、当初、私たち夫婦は共に、同じ農業大学校で花きを専攻していました。私は菊などの草花を専門に勉強していました。ちなみに、妻(当時の彼女である美穂さん)は、同じ農業大学校の一級先輩だったんです。
美穂さん
私も元々農業が好きで、農業大学校に入りました。そこで、花きの中でも、バラをメインに専攻していたので、いずれはバラ農家になりたいと志すようになりました。
そんな望さん、美穂さんのご両親は、専業農家ではなく、共に兼業で農業をされていたそうです。お二人とも、週末だけお米作りをされる親御さんの姿を見て育ったと言います。
美穂さん
農業大学校時代、農家さんに住み込みで職場体験をする一ヶ月研修がありました。私はバラ農家さんの研修を希望していたので、実際、バラ農家さんのご自宅で寝食をご一緒する中で、ご両親とご子息が家族で農業を仕事にされている理想の姿を目の当たりにし、「農業を仕事にして生きていけたらいいな」と憧れを抱き、農業を志す大きなきっかけになったんです。卒業後も、一年間、そちらのバラ農家さんで研修に行き、その後、滋賀県にある国内指折りのバラ農家さんでも一年間研修を受けました。
望さん
実は、私が農業大学校に入って、一ヶ月も経たないうちに妻と交際するようになりました。その頃から、「結婚して、一緒に農業ができたらいいね」と二人で将来のライフプランを話し合っていました。そのこともあって、私も卒業後、県内のバラ農家さんで一年間の研修を受けました。当時は、二人で「バラ農家になるぞ!」と意気込んでいました。卒業後も丸二年間は、修行のために研修に出て、その間に、父が地元の町役場で勤めていた関係で、農地の斡旋などに協力してもらいました。
美穂さん
振り返れば、卒業する前に、私の父が亡くなったのですが、生前、「地元に帰って、主人と一緒に農業をするかもしれない」と父に話していました。父亡き後、叔母から、父が喜んでいたことを伝え聞き、そのことを実現できたことが唯一の父への親孝行だと思っています。
理想と現実とのギャップ
望さん
修を終えて、私が22歳、妻が23歳の時、夢と希望いっぱいにいざバラ農業をスタートさせようと考えていました。しかし、農林水産事務所や農業協同組合の方々と協議し、事業計画書を作成していく中で、バラ農業を始めるには多額の投資額が必要であったため、新規就農する20代の私たちには難しいとの判断となり、「地元の特産品を取り入れた形での複合農業にしてはどうか」との提案を受けました。泣く泣く、地元特産の畑わさびを取り入れた複合経営でスタートさせることになったんです。
新規就農したご夫婦でしたが、初年度から壁にぶつかったとのこと。
望さん
初年度の一作目で、バラの葉っぱが黄色くなり、すべて落ちてしまったんです。ビックリしました。その時は、薬害なのか病気なのか、その判断すらできませんでした。研修先の農家さんに来てもらったところ、ベト病にかかっていることが判明し、切り落とすしかなかったんです。研修先では、病気にかかってもほんの僅かでしたので、研修と実際とでは全然違くて…。6メートル×30メートルの1棟のビニールハウスだけで栽培していましたが、全滅になってしまい大変ショックでした。
美穂さん
研修先の農家さんでは、「家庭に一輪のバラを」をモットーにされていて、私たちもやっていけるだろうと思っていましたが、販売の難しさもありましたね。食べ物とは違って、バラは嗜好品ですので、当時、なかなかお買い求めいただけず…。理想とのギャップを覚えました。
望さん
農業大学校では栽培の勉強、研修先では市場に出荷することがメインだったので、小売の知識や経験がなく、どのように販売するかを考える機会がなかったです。理想は大きく、1本100円で売ることを考えていましたが、現実は80円や50円、細いものだと30円、それでも売れない時は売れない状況です。環境が田舎ということも相まって、お墓参りで利用される菊などは好まれたのでしょうが、棘のあるバラは道の駅で販売すると、なかなか売れませんでした。それでも、利益が出なくても、自分たちのバラに対する想いが強く、やめる決断がなかなかできませんでした。バラ栽培を始めて10年。一旦休むという形で自分たちの気持ちに折り合いをつけて少しずつ野菜栽培に切り替えていきましたね。
バラから野菜への転換
美穂さん
今では葉物野菜を中心に、約20種類の野菜を栽培しています。もっと多くの野菜を栽培しましたが、今、20種類ぐらいに落ち着いたという感じです。しかし、野菜に転換した当初は、大変なことが多くありました。

望さん
バラ栽培を休止とした当時は、畑わさびだけでは収入が上がらなかったので、ハウス増設を目指して、夫婦二人で県内あちこちに中古ハウスの解体作業に行き、その中古ハウスをいただくようにしましたね。古いところは切断して新しい資材に付け替えて、自分たちの農地に建て直すことを繰り返し、地道にビニールハウスを増やしていきました。今では、21棟のビニールハウス(約50a)となりました。ここにあるビニールハウスの半分ぐらいは夫婦二人で建てました。収穫できる野菜も徐々に増えていき、農協が運営する農産物直売所に卸すようにしていきました。そんな中、ここでまた事件が発生したんです。


再びの危機発生
望さん
就農して10年、畑わさびの裏作でビニールハウスにブロッコリーを植えていたのですが、いざ販売する段階で、農協から指摘が入ったんです。野菜を出荷する際、農薬の使用履歴を表す防除歴というものを提出するのですが、農薬の名前が違っていても成分が同じことを指摘され、使用回数が1回多いことがわかり、自主回収で販売ストップとなってしまいました。4aのビニールハウス内のブロッコリーがすべて破棄。大ショックで、一週間、思考が止まりましたね。あれから5,6年はブロッコリーを栽培する気持ちになれませんでした…。
美穂さん
実際、残留農薬は出ずホッとしましたが、収入にはつながらず、苦しい時期を経験しました。
望さん
収入が落ちるので、冬のシーズンは高速道路のアルバイトをするようにしました。それまでも、夕方から夜にかけて、親戚の叔父と叔母が営む畜産のアルバイトに行っていましたが、今のように新規就農給付金はない時代なので、売り上げから運転資金と生活費を捻出することは大変でした。
美穂さん
ただ、そのことも不足の思いはなかったように思います。楽しみながらやっていました。当時は、夕方5時までここで仕事して、そこから畜産農場へ行って、帰りは夜9時を超えていましたが、それも今思えば楽しかったです。
望さん
色々苦難はありましたが、楽しみながら危機を乗り越えてきましたね。そうした苦難の経験があればこそ、今、新鮮な野菜を手に取ってくださる方々の笑顔を活力にしながら取り組み続けることができています。

多品目栽培での経営
望さん
当初は、畑わさび栽培を柱に経営していました。しかし、わさびは11月に苗を定植して5月に掘り上げと売り上げが半年もありません。裏作で、露路の畑でキャベツを作ったり、冬の収入の確保が長年の課題でした。その間、ハウスでほうれん草を栽培して市場へ出荷するなどして繋いでいましたが、1袋30円、二人で500袋、朝から収穫包装して市場へ夜中に持って行っても1万5000円にしかなりません。信用がモノを言う市場に、信用もない私たちでは仕方がないと思いました。周年で出荷し続けておられる葉物農家さんはすごいと思いました。そんな時、バイヤーさんからスーパーでの地場産コーナーをしないかとお話をいただきました。なぜうちなのかと思い聞いてみたところ、あのほうれん草を見られて評価くださったようでした。無駄なことはないなと感じ、今は毎朝、配達をして野菜を販売するスタイルになり、お客さんに楽しんで選んでもらいたくて多種の野菜を作り始め、売り上げも日毎、月毎に入る安定したものになってきました。1週間毎に葉物野菜は播種することを決めて野菜を切らさないように心掛けています。

直売の魅力
美穂さん
農協が運営する「FAM’Sキッチンいわくに」で3年前から出店するようになりました。ここでは、同世代の若手農業者の方々も出店されて、一緒に直売をしています。規格がないので不揃いの野菜も販売できて、沢山のメリットを感じています。普段は、野菜とばかり向き合っているのですが、実際、対面でお客さんが、自分たちの野菜を手に取ってくださる様子を見られることは嬉しいです。「どのように料理して召し上がっていますか?」とお客さんにお聞きすると、「これね、こんなふうにしたら美味しいのよ」と答えてくださったりして、栽培している野菜のその先にお客さんの笑顔があることを実感できます。それに、「のぞみファームの野菜は綺麗で美味しいから買おう」というお声もお聞きし、ファンがいて下さることも力になりますね。ビニールハウスで農作業に当たってくださっているスタッフさんにも、お客さんからの喜びのお声や、店頭での野菜の写真などをグループラインで発信し、農作業の先に何があるかを共有するようにしています。
望さん
私も農協の関連で、青壮年部の直売を担当していて、徐々に慣れていきました。直売でのお客さんとのやりとりの場がもっとあれば、スタッフさんの遣り甲斐にもつながるはずと思っていたところ、RINRI PROJECT主催のETHICS FAN MEETINGでも物販が始まったことを知り、そこに出店するようになったんです。ですから、ETHICS FAN MEETINGの際には、スタッフさんにも手伝っていただいて、立ち寄ってくださる方々との交流も生まれました。
次世代への農業継承に対する想い
望さん
フルタイムのスタッフさんがお二人いらっしゃいます。お一人は、農協系の求人サイトを見て応募くださり、実は、中学・高校時代の私の同級生の方でした。そのパートさんの娘さんが就職活動をしていることを伺い、高校生の娘さんが農業に興味を持っているとのことで、職場体験としてうちに来てくれました。本当は社員として迎えたい気持ちもあったのですが、その余裕がないため、「フルタイムのパートでもよければうちに来ませんか?」と提案したところ、昨年4月よりうちに入社してくれたんです。
望さん
中学生の職場体験の引き受けや、収穫体験などを行なっているのですが、田舎に住んでいても、畑の野菜を触ったことがない児童が増えてきていることに大きな危機感を抱き、若い人への農業継承を真剣に考えるようになりましたね。
美穂さん
キッズ世代を対象に、ミニトマトやほうれん草、ズッキーニ、それにお米の収穫体験や、グラム数を量るぴったり賞などを企画して、地元のお子さんに農業体験の場を提供しています。その取り組みもあって、私たちも、若い子にもっと農業に携わってもらい、農業を仕事にすることを選択肢の一つにしてほしいとの思いが更に大きくなっていきました。
望さん
私が農業に興味を持ち、農業大学校に入ろうと思った一つのきっかけは、小学生時代、子供会のイベントで農業大学校の体験会に参加したことでもありました。その経験がずっと頭の片隅に残っていて、農業という道を選択する大きなきっかけになっていたように思います。ですから、農業体験の場を提供したり、若い子と実際に一緒に働きたいという思いはずっとありましたね。
美穂さん
若いスタッフさんの意見は貴重だと感じています。例えば、商品に貼るシール一つにしても、意見を聞くと色やデザインなど、私の中にある固定観念を破ってくれて、参考にさせてもらっています。マルシェで知り合った隣町のお菓子屋さんと、野菜を使ったお菓子作りについて話したところ、早速、その子がほうれん草を使ったマフィンを作ってきてくれたりするんです。
望さん
これまでは、主に収穫・包装の担当をしてもらっていましたが、将来は野菜を自分で育てているという遣り甲斐を感じてもらうために、ビニールハウス毎に担当制にできたらと考えています。また、他の生産者との接点も持てるよう、配達などにも携わってもらえたらと思っています。今年、20代のスタッフさんには農業用大型特殊の免許を取りに行ってもらいました。いずれは、野菜部門とお米部門のように分けられたらいいなとも考えています。自分たち二人で考える農業では、時代についていけなくなってしまうので。
ちなみに、余談ですが、その子がヘアドネーション(病気や事故などで髪を失った子どもたちに、寄付された髪の毛を使って医療用ウィッグを無償で提供する活動)をしていたので感銘を受けて、私も一年半前からヘアドネーションのために髪を伸ばしています。31センチ以上必要なので3年はかかります。悪戦苦闘しながらですが楽しんでいます。このようなことも若いスタッフさんの影響を受けているんですよ。
障がい者支援施設との連携
望さん
今年、途中で一旦やめることになったのですが、就労継続支援B型(障がいや年齢、体力などの理由で雇用契約を結んで働くことが困難な人が、就労の機会を得たり、就労に必要な知識や能力の向上のために就労訓練を受けたりすることができる障がい福祉サービス)と契約し、週2,3日ほど、3,4名の方が、うちの農作業で働いてくれていました。施設の中で作業をされていたこともあり、外での農作業は喜んでやってくれました。ビニール貼りや遮光ネットの片付けなど、色々な作業がありましたが、本当に丁寧に作業に当たってくれていました。働く喜びを提供させてもらうことも社会貢献と考えています。
里親制度への登録を決意
農業とは別に、里親の顔を持つ隅さんご夫婦。日本には親御さんと離れて暮らす子どもたちが多くいる状況下、温かな家庭で愛情を注いであげたいとの想いを抱くこととなります。
望さん
結婚して10年が経った頃、子どもができなかったこともあり、養育里親と養子縁組里親の両方に登録することにしました。6年前、県内にある施設の小学二年生のお子さんを週末、お預かりすることになったんです。中学生になると、部活や友達との関係もあるので、里親のもとには行かなくなるケースが多いようなのですが、その子は、ありがたいことにうちに来たいと言って、週末になる度に施設に迎えに行っていて、お互いに良い関係が築けたと思っています。
美穂さん
一緒に野菜の収穫や商品のシール貼りをして楽しそうに手伝ってくれ、私も一緒にできて嬉しいです。
望さん
大きな施設で育つお子さんの場合、家族や家庭のことは何もわからずに育つことになります。農業に触れたその子が、「お父さんに食べさせてあげたい」といった感情になった姿を見た時、農業をやりながら里親として、家庭の在り方を伝えていけることはいいなと思いましたね。ニュースで報道される実態は本当に氷山の一角でしかなく、辛い境遇のお子さんが多くいることを思うと、少しでも社会の役に立てたらと思って引き受けています。私たちにとっても、いい勉強になっています。
農業士・農林漁業ステキ女子を通して
望さん
岩国地区の農業士会で、来季、誰が会長をやるかという話になった時に、「自分がやってみたいです!」と手を挙げました。お役を通して、自分の成長があると思っているからです。今年、3年目になりますが、その前は、日本の農業を支える20~30代の若い農業者を中心に活動する4Hクラブ(農業青年クラブ)で、地区、県、中四国の会長も経験させてもらいました。農業者人口の高齢化、農業離れ、耕作放棄地の増加など、抱える課題は山積していますが、農業振興に携わるようになって、第三者の方に農業を継承していくという想いも強まり、地元の高校から新卒を採用しようと思ったのも地域貢献の一環になると思ってのことです。
美穂さん
私は岩国地域ステキな農業女子セミナーに参加して、野菜の保存方法や、作業場の改善などの講習を受け、自己流ではなく専門的な視点で改善しています。例えば、「野菜を入れるのは、冷蔵庫がいいのか、野菜室がいいのか」と、お客さんから聞かれることもあるので、そのような時、「この野菜は濡れ新聞紙に包んで野菜室に入れるといいですよ」と、専門的にお答えできるようになりました。また、事務所内の動線を見直し、パートさんがわかりやすいようにホワイトボードを活用して色々と工夫するようにしました。みんなが気持ちよく働ける環境づくりを考えるようになりましたし、講習を通して、それまで横のつながりがほとんどなかったのですが、北海道から沖縄まで、多方面の女性農業者の方々から、とても刺激をいただいています。

今後のビジョン
望さん
この地で、自分たちが収穫した野菜を使った加工品を提供したり、人が集まれる農業体験・食の提供から農業の魅力を発信する場をつくっていきたいと思います。そして、本郷町にもたくさんの人が来てもらいたいです。
美穂さん
先程のほうれん草のマフィンもそうですが、野菜作りにとどまらず、野菜を使ったお菓子や加工品も提供していきたいですね。そして何より、私たち夫婦がこれからも和気藹々と農業に従事することで、職場全体、そして地域の活力につながっていければと思っています。
最後に
望さん
“作ってみたい”“やってみたい”ができる、そこが農業の魅力だと思います。今まで50種類ほどの色んな野菜を作ってきました。野菜のカタログ(タネ)を見るとワクワクして、つくづく二人とも作ることが好きなんです。しかし、経営をしていかないといけないので、利益が残らないと好きな農業も続けられないことを資金難になって気づく始末で、売れる野菜の面積を増やし、利益の低いものはやめていき、今は20種類ほどになりました。自分で考えて新しいことにチャレンジする農業の醍醐味もあり、失敗も楽しめています。これからも新しいのぞみファームを作っていきたいと思います。
美穂さん
主人の新しいことにチャレンジする精神、諦めない粘り強さ、丁寧な仕事があればこそ続けてこられたと思います。そして、就農前の研修期間が今、仕事に向かう姿勢の基礎になっていることを感じています。これからも二人で、就農当時の夢や希望いっぱいの心を忘れずに希望を実現していきたいです。少しでも農業の魅力を主人と発信し続け、選ばれる農家へ、そして次世代へ農業という仕事を繋げていきたいです。

今回は、隅さんご夫婦にお話をお伺いし、農業に懸ける信念の強さ、農業の枠を超えて次世代に愛情を注いでいく温かさ、社会貢献への展望が伝わってまいりました。農作業をされるお二人は、とてもイキイキされていて、農業を愛する様子が窺えました。
ぜひ、皆さんも、お近くに行かれる際には、自然豊かな土地にあるのぞみファームを訪ねてみてください。新鮮で美味しい野菜が味わえますよ。
のぞみファームの情報
住所:〒740-0603 山口県岩国市本郷町波野1607-1
アクセス:山陽自動車道岩国ICより車で約35分
錦川清流線河山駅より車で約12分