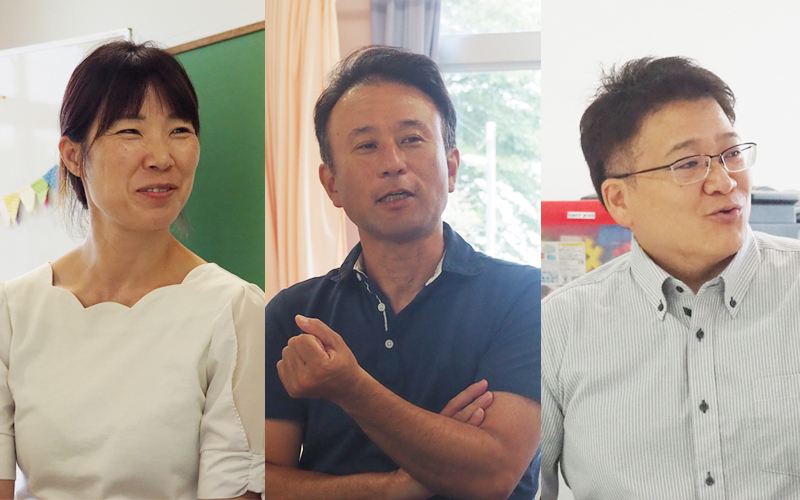活動
2025.09.17
「島民の医療の課題」下甑手打診療所
甑島列島の下甑島最南端に位置する手打、白い砂浜の手打湾を望む丘の上に、薩摩川内市保健福祉部の管轄下にある下甑手打診療所はある。
「Dr.コトー診療所」のモデルである瀬戸上健二郎先生が、長年にわたり離島医療に尽力された診療所である。
高齢化率は50%を超え、2人に1人は65才以上の下甑島。人手不足、資源不足という課題も抱えるこの島で、今、手打診療所の所長として島民の命と生活を支えておられる室原誉伶先生にお話を伺いました。
 |
 |
|
|
所長 |
ご質問① 東京の河北総合病院で研修をされていたのですね。研修時代はいかがでしたか?
初期研修は3年間あったのですが、診療科毎に3ヶ月ずつ勉強することができました。各科の研修をまわりながら、どれも楽しく将来の診療科を一つに絞り込めませんでした。
ご質問② 離島医療を選択したきっかけを教えてください。
全国のへき地・離島にある病院と連携し、へき地・離島で働ける医師を育てるという1年3か月のプログラムを提供している「ゲネプロ」という団体があります。そのゲネプロを通して、河北総合病院での初期研修後は、長崎の五島列島の病院で内科研修を1年間、モンゴルの病院で3か月間研修を受けました。そうしたへき地・離島での研修を通して、ジェネラルに診療していく医師のスキルの高さに大きな衝撃を受け、総合診療医が求められている地域があることを知ったんです。その後就職した、島根県の隠岐諸島にある隠岐島前病院での勤務も通して、離島医療の面白さを実感しました。
ご質問③ 島での暮らしはいかがですか?
身の回りの空間や時間に余白があっていいですね。都会で過ごしていると、忙しさで心を落ち着かせて考えるゆとりがなくなってしまいがちです。島での暮らしは考えたり行動する余白があるので、固執することなく柔軟な発想で生きることができます。
ご質問④ 2019年に下甑手打診療所に副所長として着任されて、当時ぶつかった課題はどんなことでしたか?
ここでは、介護保険において、どれだけ高い介護度になったとしても、フルの介護度を使えるリソースがないんです。介護士の人材が不足しているため、例えば要介護5の患者さんがいたとしてもフルの支援を受けられない状況。当時は、訪問看護師1名、訪問ヘルパー2名のみでしたから、とてもカバーし切れないという壁にぶち当たりましたね。90歳まで生きてきたのに、最後の最後で好きに生きられないというのは侘しいものです。甑島のような地域では、医療・介護・福祉などと区別していては、患者さんの要望に応えることはできないと思い、患者さんが望むような最期を迎えられるよう生活支援サービス、 “御用聞き”(「御用聞き」は東京などで展開されている既存のサービスです。そののれん分けのような形で運営させてもらっています)を始めようと思ったんです。
地域のケアマネージャーさんに、どうしたら高齢の患者さんは島で長く暮らせるのかを聞いてまわったところ、身近な電球交換や庭の草むしり、お墓掃除など、些細なことで困っている状況を知り、そこで生活の隙間に入れるサービスの重要性を教えてもらいました。
この診療所での2年間の任期を終えた後、夫婦で生活支援サービスをスタートさせました。所長として再び診療所に戻った今は、病院勤務が中心なので、妻が主体的に支援サービスを行なっていますが、こうしたサービスこそ島には必要なんです。
ご質問⑤ 生活支援サービスで特に喜ばれたことはどんなことでしたか?
脳梗塞を患い、お一人暮らしで長年家から出られずにいらっしゃった80代の男性から、「一度でいいから、甑大橋を渡ってみたい」とのお声を寄せてもらいました。車でお乗せして、甑大橋を渡った時には大変喜んで下さいました。
島でずっと暮らしていたいという方でしたが、その後、頭の中に出血が見つかりました。手術をしてリハビリをすればまた島に戻って来ることができると伝えて、その方を二、三回説得して本土で治療を受けてもらいました。しかしその後は、下甑島に帰ることはできず現在も本島の施設に入所されています。しばらくしてご家族が御挨拶に来て下さり、その方のリハビリの様子を動画で見せて頂いたのですが、とても良い笑顔でした。説得して、「また島で暮らしましょう」と送り出したことへの後ろめたさがありましたが、島で暮らせなくなったからといって不幸になるとは限らないことも教えてもらいました。

▲下甑島と中甑島を結ぶ「甑大橋」
ご質問⑥ 今後の離島医療について、どのようにお考えでしょうか?
最近の人口減少は著しいです。今まで地域を支えてこられた方々も様々な施策をして、アプローチをし、努力をしてきた結果が今なので、この人口減の現実は抗えないものと思っています。私が下甑島に来た6年前は、人口2000人弱と言われていましたが、今では1500人を切っています。お亡くなりになる方もおられれば、島外に行く方もおられるのだろうと思います。人口増を目指すというよりは、この島に残った方々、この島で暮らしたいと願う方々の暮らしに選択肢を提供できるようなサポートをしていきたいと思っています。
ただ現実的に、人口が減っていった時に私たちはどこまですべきなのか、この島には入院施設はあったほうがいいと思っていますが、500人の島であれば入院施設はない地域もあります。この島の人口が例えば500人程度まで減った時に入院施設を維持し続けるべきなのか、本土の入院施設とどう連携していくのか、そういったところは課題として浮上してきます。
一方で、離島医療で一番養われたと思うことは、相手のニーズを見抜く力ですね。この患者さんは何のために病院に来ているのか、もし満足させることができなければ本土の病院に行ってもらうことになってしまうので、患者さんが求めておられることは何かを真剣に模索するようになりました。薬がほしいのか、診断がつけば安心なのか、専門的な検査をすれば納得するのか、それは人それぞれ違うので、離島3ヶ所目ですが、離島医療を通して相手のニーズを知る力を培うことができたと思っています。
ご質問⑦ 今後のビジョンについて教えてください。
祖父が開設した熊本の病院があり、今は父が引き継いでいます。いずれは私も帰らなければならないときが来るとも思っています。ただ、総合診療医として、甑島の環境で働けることは幸せなことだと思っています。
将来的には、総合診療医を育成できるシステムを作って、月に数回、手打診療所に派遣できるような仕組みを整えられれば、安定した運営ができるはずです。今のような二人体制の医師では、一人が欠けた時に、もう一人にかかる負担は多大なものがあります。ですから、同じ教育を受けた医師が均一的な医療を施することのできる派遣システムを構築できればと模索中です。別の病院で学んだことをここで生かし、ここで学んだことを別の病院で生かす、そうした経験を積むことで医療の質を高めていくことにも繋がります。
私自身も、将来的に拠点が熊本の病院に変わったとしても、甑島での医療に携わり続けていきたいです。

▲診療所の屋上からの眺めが絶景と室原さんに教えていただき……まさに絶景でした!
離島という過酷な環境の中でも、島での暮らしを望む住民の方々の心の声に寄り添いながら、島民の生き方と暮らし、そして命を支える室原先生の取り組みは、医師という枠を超えた総合的で人情味溢れるサポートでありました。
時に、医師という肩書きを捨てて農業に軸足を置き、昔の田園風景を蘇らせ、美味しいお米を提供したり、御用聞きとして島民が悩んでいる困り事に手を差し伸べたり、ニーズを捉えて縦横無尽に応えていく。そうした室原先生の生き方は、離島医療の発展と今後の甑島を支える大きな力なのではないでしょうか。
私たちRINRI PROJECTは、これからも下甑手打診療所を応援していきます!